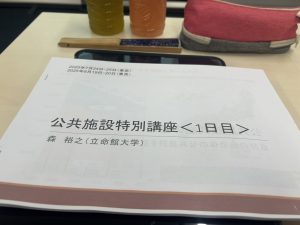2025年8月20日 | 活動報告
本日は公共施設特別講座2日目。

③10:00~12:30
『公共施設更新費用と財政的な視点』
④13:30~16:00
『インフラ老朽化の課題』
③では財政を専門とする財政的な視点からの説明で始まり、国費や地方債の考え方については元財政課職員でしたのでよく理解は出来ました。
国の制度や予算をどう活用するかによって今と後年度の負担がかなり変わってきます。
それに加えてどの起債の種類があたるかによっては交付税参入があるか無しかで財政的な負担も変わります。
等級化した施設の更新に関してはどの自治体も悩ましい問題です。
予防保全の観点から長寿命化をして活用し続けることが基本的な考え方になると思いますが、人口減少に伴い全体的な送料の抑制も考えないと維持修繕にかかる費用は増えるばかりです。ましてや利用者の事も考えると例え公共施設であろうとランニングコストを賄える収支見通しを立てないと赤字の垂れ流しでは立ち行かなくなります。
公共施設の集約化・複合化も視野に入れながらこれからの住民ニーズに合った公共施設の在り方を今から研究検討していかないと取り敢えずの延命治療だけではツケを後年度に回すだけだと思います。
④では主に自治体が担う土木関係の投資の更新時期を迎えるにあたり、その中でも道路、上下水道菅、橋梁など老朽化によって全国的に事故が生じている事例も交えながら対応の必要性を学びました。
本市は平地で面積も小さい自治体であることから、あらゆる面において効率的に税の活用をすることが出来ています。
基幹管路の耐震化も100%達成し、災害時にも住民の暮らしを守ることを第一優先で市政を進めて頂いています。
早くから進めた下水道も普及率が高く、衛生的にも安全性にも優れた街並みが実現していますが、老朽化した下水道管の更新も今後必要となっています。
そのような状況において全国的に技術系職員の採用問題を抱え、今後益々必要性が高まる職員の不足が課題となっています。
小規模自治体では職員の数も不足していて、土木と建築のそれぞれの分野のバランスの整った職員体制は望めない中での市政運営の舵取りは非常に難しいものと感じました。
必要な人材を自前で育てる発想もこれからは必要な時代なのかと思ったりもします。
自治体職員がかなり転職等で流動的になってきている昨今、働き甲斐の有る職場づくりにも傾注しなければならないと改めて感じた次第です。
2025年8月20日 | 活動報告
今朝は6時15分新大阪駅発東京駅行きの新幹線に乗り込んで、新宿にある会場で10時からの公共施設特別講座を受けました。
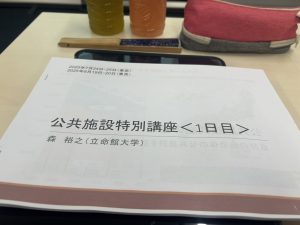
①10:00~12:30
『公共施設問題の基礎』
②13:30~16:00
『学校統廃合と公共施設問題』
議会で配られた地方議員研究会が主催する講座案内チラシのこのテーマに目が留まり、直ぐに申し込みました。
本市でも全国の潮流にあるように公共施設の今後の適切な維持管理が問われています。
人口減少社会であり高齢化を迎え、公共施設をこのまま維持管理していくことの問題点を講師の立命館大学政策科学部の森教授から説明され、今後住民にかかる負担が重くなるのは必至です。
人口急増時代に増えた公共施設の一人当たりの延べ床面積をどう減らしていくか、どの自治体とも大きな課題がのしかかります。
①の基礎講座では財政的な見地からこのままでいくことの適当なサービス配分が可能かどうかの問題点を分かりやすく教えて頂きました。
適切な公共施設のマネジメントをしなければ、維持管理費に予算が費やされ、一般財源等を他の政策に振り向けることが出来なくなります。
参加されている議会の一部の状況を分析しつつ、先進的に取り組んでいる自治体の事例をもとに講義が進みました。
公共施設の整理の仕方について何が正解で不正解かはありません。
その土地土地の課題は様々で、色んなケースを知ることで引き出しを多く持つことが肝要なのだと学びました。
②では特に公共施設の延べ床面積の多くを占める教育施設をどのように縮小方向へ導くか。
アプローチの仕方や環境が違う中で、松原市にあった考え方を見つけていかなくてはいけないですが、一体誰が絵を描き推進していくのか。
地元から上がっていくことが最も円滑に進むような気もしますが、地域を巻き込んでの統廃合するパワーは想像を絶するものだと想像します。
講師からは、廃校する側の学校の利用も同時に考えないと上手くいかないとの貴重な見解をお聴きし、地域ごとの合意の下で統廃合を進めなければならないのなら、そう簡単には物事が進まないことを改めて思い知らされる研修第1日目となりました。
建設すること以上に整理することの理屈をどう住民に理解して貰えるかが重要となります。
良いものに建て替えることが出来れば住民の理解も進みやすいですが、ただ単に無くすということはかなりの説明責任が必要です。
市政を担うリーダーとして決断することが求められますが、政治家としては出来るならば避けたい分野であることも事実です。
しかしながら先延ばしすることによって、今後益々多様化する住民サービスの質と量を狭めないように注力しなければその自治体の明るい未来は開けないこともまた事実だと思います。