今朝は6時15分新大阪駅発東京駅行きの新幹線に乗り込んで、新宿にある会場で10時からの公共施設特別講座を受けました。
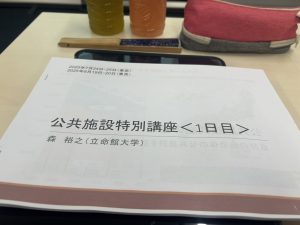
①10:00~12:30
『公共施設問題の基礎』
②13:30~16:00
『学校統廃合と公共施設問題』
議会で配られた地方議員研究会が主催する講座案内チラシのこのテーマに目が留まり、直ぐに申し込みました。
本市でも全国の潮流にあるように公共施設の今後の適切な維持管理が問われています。
人口減少社会であり高齢化を迎え、公共施設をこのまま維持管理していくことの問題点を講師の立命館大学政策科学部の森教授から説明され、今後住民にかかる負担が重くなるのは必至です。
人口急増時代に増えた公共施設の一人当たりの延べ床面積をどう減らしていくか、どの自治体とも大きな課題がのしかかります。
①の基礎講座では財政的な見地からこのままでいくことの適当なサービス配分が可能かどうかの問題点を分かりやすく教えて頂きました。
適切な公共施設のマネジメントをしなければ、維持管理費に予算が費やされ、一般財源等を他の政策に振り向けることが出来なくなります。
参加されている議会の一部の状況を分析しつつ、先進的に取り組んでいる自治体の事例をもとに講義が進みました。
公共施設の整理の仕方について何が正解で不正解かはありません。
その土地土地の課題は様々で、色んなケースを知ることで引き出しを多く持つことが肝要なのだと学びました。
②では特に公共施設の延べ床面積の多くを占める教育施設をどのように縮小方向へ導くか。
アプローチの仕方や環境が違う中で、松原市にあった考え方を見つけていかなくてはいけないですが、一体誰が絵を描き推進していくのか。
地元から上がっていくことが最も円滑に進むような気もしますが、地域を巻き込んでの統廃合するパワーは想像を絶するものだと想像します。
講師からは、廃校する側の学校の利用も同時に考えないと上手くいかないとの貴重な見解をお聴きし、地域ごとの合意の下で統廃合を進めなければならないのなら、そう簡単には物事が進まないことを改めて思い知らされる研修第1日目となりました。
建設すること以上に整理することの理屈をどう住民に理解して貰えるかが重要となります。
良いものに建て替えることが出来れば住民の理解も進みやすいですが、ただ単に無くすということはかなりの説明責任が必要です。
市政を担うリーダーとして決断することが求められますが、政治家としては出来るならば避けたい分野であることも事実です。
しかしながら先延ばしすることによって、今後益々多様化する住民サービスの質と量を狭めないように注力しなければその自治体の明るい未来は開けないこともまた事実だと思います。
