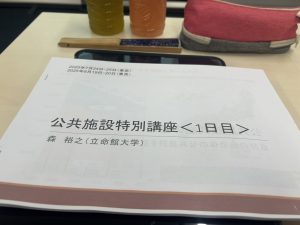2026年1月25日 | 活動報告
2026活動報告チラシvol.17

2026年丙午の年が明けてしばらく経ちました。
今年は迷信を気にして出産を控えられている動きが出ているとも言われています。
ただでさえ少子化なのにこれ以上少なくなってはいかがなものかと心配してもどうにもならないけれど、どうにかしなくてはなりません。
そもそも政治がどうにか出来る事なのか…
子育てにかかる負担を解消すれば子どもを産むのか…
家族に対する価値観が変わりすぎてしまったからではないかと思うところ。
昔は共同生活があって、その中で各家庭は身を置いてきたが、家族と言う最小単位の社会でも個人で生活できるといった意識が芽生えている気がする。
となれば、家族がそもそも必要なのか…
自分一人でこのまま老いても最後は福祉が面倒見てくれる、なんて考えている人も少なくないような気がする。
スマホがあれば何でも出来る時代。
仮想的にもつながることが出来、都合の良い時だけ自分の見方をしてくれる人と繋がればよい。
寂しさも感じないからこそ、リアルに繋がることを不必要と感じ面倒にも思う。
だからこそ生身の人間ではなく、2次元の人と結婚しようとする人さえ出てきている現代。
これからの社会で「つながり」を訴えて響く人はどれだけいるのだろうと思う。
繋がることの大切さを知っている人は理解できるが、知らない人にはわずらわしさしか残らないような気がする。
古き良き時代を誰が訴え、誰がその良さを享受できるのか。
その疑問と戦いながらも「まちづくり」を進めていかなくてはならない。
日頃からの地域の繋がりを今一度大切にするしかないのだけれど…
2025年12月3日 | 活動報告
令和7年12月2日(火)午後1時
本日、個人質問第1日目の3番目として演壇に立ちました。

◆質問通告内容
1.経済対策について 1.国の総合経済対策を踏まえた本市の対策について
2.大阪・関西万博について 1.万博の総括とレガシーの継承について 2.万博首長連合の今後の展開について
3.市民協働について 1.町会・自治会の負担軽減施策の現状と今後の見通しについて
4.青少年の非行防止と健全育成について 1.松原市の少年非行の実態と非行防止対策並びに健全育成の取組について

1.経済対策について 1.国の総合経済対策を踏まえた本市の対策について
11月21日に閣議決定された国の総合経済対策を踏まえた本市の物価高対策について質問しました。
補正予算が18,3兆円組まれ、その内総合経済対策関係費が17,7兆円で大半を占めています。
中でも国民に関心の高い生活の安全保障・物価高への対応に8兆9041億円が充てられます。物価高対策では、冬場の電気・ガス代支援に5296億円を充てるほか、地方自治体が活用できる交付金を2兆円拡充し、食品向けに特別枠を設けられます。これから年末年始に向け様々な出費が家計を圧迫することが予想される中、いわゆる重点支援地方交付金の使途が住民には特に気になるところ、現時点でどの事業に充てるか、また新しい事業を立てるのかは検討段階であるというものの早めの対応をお願いしたい。
昨年12月に一家庭5キロのお米が市から配布されたが、今回は松原市は約9億円の配分ということで、全世帯を対象となる施策とすれば、値が高止まりしているお米を一人に5キロを配布し、市内米穀店も配達で参入できるようにすることでより喜ばれる活用の仕方を決断して貰いたい。
お米券の配布については経費が掛かってしまうと批判もされているところですが、米価が高止まりしている現状では世帯員数による生活必需品に目を向けるべきです。現金支給は家庭的に問題があるところは行き渡らない可能性もありますので適切な判断をお願いしたい。
2.大阪・関西万博について 1.万博の総括とレガシーの継承について 2.万博首長連合の今後の展開について
今年4月13日に開幕し、184日間多くの来場者を迎え数多くの賑わいを創出した大阪・関西万博も10月13日に多くの人に惜しまれながら閉幕しました。会場では数多くのギネス記録が生まれ、並ばない万博がウリでありながらも結果的には長時間並んでも多彩なイベントに依るところもあり、予想以上に来場者の満足度が大きく、そこで多くのレガシーも生まれた記念すべき万博になりました。
本市にとって賑わいを呼び込む取り組みをされてきていましたが、中でも未利用チケットをお持ちの方の救済措置には多くの人が反応を示し、松原市に対する評価も上がったのではないでしょうか。
利用できた人の数は全体的な母数からすれば知れていたにせよ、気持ちがある取り組みに心が温まった気がします。
さて、会場内での周知イベントも盛りだくさん行われ、松原市が他市にアピールする機会を最大限利用しつつ、万博で生まれたレガシーがどれだけ生かせ、また本市市長が現会長である万博首長連合の今後の展開について問いました。
市長答弁では『万博を通じて全国の自治体や企業、大学などとのネットワークが飛躍的に広がったことから、名称を「地方創生を通じて、日本の未来社会を創造する首長連合」(通称「日本首長連合」)と改め、地域同士が「共創」により広域的に連携し、地方創生を進めていく方向性が示されております。国の地方創生の基本方針とも連動し、地域資源の磨き上げや広域プロジェクトの推進など、全国て‘連携を深めながら取り組む枠組みが進められている』とのことです。
議謡的な事はこれからのようですが、住民どおしの交流も促進されるような施策も期待したいところです。
今回の万博で様々な機会を捉え、職員が一丸となり、また専門的スキルをもつ観光協会の頑張りがあってこそ乗り切った半年間だったと思います。
大変お疲れさまでした。
3.市民協働について 1.町会・自治会の負担軽減施策の現状と今後の見通しについて
令和7年度から、町会・自治会の負担軽減のための「ジチカン」と言われるアプリ導入とポイント制報奨金制度が始まりました。
アプリについてはまだ導入している町会が無かったために敢えて質問しませんでしたが、現段階での状況がどうか、今後の見通しをどう考えているかについて質問しました。
ポイント制度は活動内容SNSで発信しすると一回について200ポイント(1ポイント100円)で5回までポイントが付与されます。
つまり、年度末に申請した後、町会の会計に最大10,000円が振り込まれる仕組みです。その他新規加入者につきポイントも加算されます。
そういったインセンティブを活用すれば多少なりとも収入が増えますが、SNSを使う役員さんが高齢者の為ハードルは決して低くありません。
そういったことから、今後のんびり構えていては益々町会の衰退に拍車がかかる懸念から更なる施策を打たないといけないと思い、質問提案しました。
昨年12月にまつばらテラスで開かれた「まつばら共創ミーティング」で講師として招待された金子陽飛さんが高校生の特にとあることから町会長を務めることになり、周りもそれに対して協力をし、活気づいた成功事例を聴きました。
つまりは高齢化した役員さんがどれだけ頑張ろうとしても大方新しいことへのチャレンジは期待出来ませんが、若い世代の発想力と行動力でこの難局が乗り切れないかと言う視点で提案をしています。
何もしなければそのまま崩壊の一途を辿るしかない町会活動も若い世代のチカラで再生の道を歩んでいくべきであると次のステップとしての更なる取組を市に対して求めました。
4.青少年の非行防止と健全育成について 1.松原市の少年非行の実態と非行防止対策並びに健全育成の取組について
今年の夏休みに近所の大型ショッピングモールのフードコートの一部が、たむろした未成年たちによって営業妨害された事件が続きました。
その事を知ったのが学校も始まった9月でした。
もう調査した時期には落ち着いていましたが、店舗のマネージャーや警備担当の代表者、その次にモールの支配人から起こった内容を聴き取り、我々に何が出来るのかを思案し、とりあえずは少年の非行防止に向けた既存会議の在り方の見直しを教育委員会に求め、学校と警察だけでは手に負えない状況に関係団体が協力し合って取り組まなければ、他市から流れてくる面の割れていない非行少年に松原市の子ども達が犯罪に巻き込まれている危険性を訴えました。
教育委員会としても事態を重く受け止め、「各校での専門家を交えたケース会議の充実や学校警察連絡会など関係機関との連携を更に進め、地域社会全体で子ども達の安全と健やかな成長を支える環境整備に努める」との教育長の答弁がありました。
今後スマホの普及によって、犯罪の益々の低年齢化が懸念されています。
物事の良し悪しが分からない内に手を染めることがないように、大人が食い止めなければ令和4年に全国的に増加傾向に転じた少年犯罪は松原市においても増え続ける中、「安心安全なまち」とは到底言えないことを演壇で申し上げました。
青少年対策会議のメンバーである町会関係者の一人として何が出来るか、他の団体の代表者と共に考えなければなりません。
2025年11月12日 | 活動報告
◆令和7年11月11日(火) 午前9時00分~12時 於:島根県伯耆町清掃センター・町営温泉施設「ゆうあいパル」
◆視察対応者:(株)スーパー・フェイズ顧問・前町長森安保氏と町職員で地域整備課行政専門員の井本達彦氏
伯耆町に「使用済み紙おむつ燃料化事業」を視察することになったきっかけは、燃料化装置を開発された(株)スーパー・フェイズの坂本さんからのメールだった。
全会派一致で決まった令和6年3月定例会(第1回)の意見書の中において、紙おむつ等の地域の循環資源や木質バイオマス等の再生可能資源の活用などに触れていたことにヒットされたことで私のHPへ問い合わせを頂いたことからやり取りが始まった。
以前から老朽化している市民プールの温水プール化を提案していたが、光熱費がかかることから提案がしにくい環境であった。
使用済み紙おむつを燃料化することで燃料費が抑制されるのではないかと思い、大阪市の平野清掃工場の余熱を利用できない場所に建設するなら環境教育、CO2削減の観点からも燃料化をして精製されたペレットを用いたバイオマスボイラーを活用して温水プールを運営し、問題となっている小中学校の水泳授業と高齢者の健康増進の拠点として、あるいはレジャープールとしての機能も持ち合わせた施設の建設を訴えていることから、より説得力をもった提案が出来るものとして直ぐに会派視察を決めたものである。
朝一番のスケジュールをご提案頂いた関係で前日から島根県に入り、9時からの視察に伯耆町清掃センターを訪れた。現場では(株)スーパー・フェイズ顧問で前町長である森安保氏と町職員で地域整備課行政専門員の井本達彦氏、それと燃料化設備のオペレーターの男性に聴き取りと機械の操作を視させていただいた。


一日当たり400~500㎏のビニル手袋やおしりふきシートも含まれた使用済み紙おむつを、臭気を抑える一枚5層の60円の割高な袋に入れた状態で6つの介護施設や5つの保育所からオペレーターが収集されてきます。



次の作業として燃料化装置に投入して16から18時間で滅菌処理がされたフラフが、重量が三分の一になって排出されます。その後、ペレットを作る別の装置にそのフラフが投入され、ペレットとして精製されます。



一連の作業の流れの現地説明を受けた後、ペレットを燃料としたバイオマスボイラーを運転する「温泉施設ゆうあいパル」に場所を移し、建屋込みで3500万円するボイラーの見学をしました。


ボイラーが小さいとそれだけ燃焼効率も悪く、かと言って点火したり消したりすると熱効率も悪く、すすが必ず出るので燃やし続けて運転しているとのこと。ボイラー自体の調達が難しく、今後の運用が懸念されます。
場所を施設内の会議室に移し、質疑応答の時間を取って頂きました。

ボイラーの選定・開発にかなり苦慮されたようですが、そもそも精製されたペレットの活用に苦慮されたことで、しっかりとした使用済み紙おむつの活用プロセスの一連の流れが定まっていることが条件であり、その条件が整うことがかなり困難を極めるのだと学びました。出口対策がしっかりできていないと、つまり、多額を費やしてペレットを精製したものの、そのペレットの活用が上手くいかなければ事業としては低い評価が出されます。
そこで高い評価を実現するために多額の税を更に大きなボイラーに投入するにしても市民や議会の理解を得られるのかとの疑義が生じます。
そもそも伯耆町は行財政運営の面から2つの清掃工場を1つにすることが命題にあり、処分する可燃ごみの量を減らすためには使用済み紙おむつの再資源化が有効であるとの結論が出たことからの高額な投資とも考えられる燃料化装置やバイオマスボイラーの導入に至ったと聴きました。つまり出口戦略が不十分であったように感じました。
当初、町ではこれらの一連の装置の整備には過疎地域特別債や合併対策債を活用しています。町議会にはトータル的なごみ量が明らかに減っているとの説明から説得されたとのことですが初期投資がやはりかかっていることにも注視しなければなりません。費用対効果はもっとも求められることであり、本市においてもそれだけの投資をしてまでバイオマスボイラーが有効的に働くかどうかである。
繰り返しになるがしっかりとした出口戦略が定まっていないと装置の設置に踏み切れるかどうかの説得力に大きな影響が出る。そのあたりの率直な説明が資料からだけではなく、実際に足を運んだ今回の視察で学べたことが今後の判断に大いに役立つことになった。
長時間に渡り、視察を受けて頂いた両氏に対し心から感謝申し上げます。
2025年9月19日 | 活動報告
令和7年9月16日(火)
2番目として質問に立ちました。
公共施設について
1.市民プールの施設及び利用の現状と今後について
2.学校プールの施設及び授業の現状と今後について

全国的に問題となっている公共施設の老朽化。
今回焦点をあてたのは市民プールと学校プールです。
人口減少に伴って、一人当たりの公共施設の延べ床面積も縮小方向にしていかなければ財政的に長期的には持たないことから今から整理統合していく必要があります。
松原市では市民プールは昭和61年に建設されて40年。学校のプールについては人口急増期に校舎と共に建てられて各校50年前後経つこともあり、これからの在り方について質問提案しました。
市民プールは平成30年に約6000万円をかけて大きな改修もしながら10年の寿命が近づいてきています。
学校プールについては大規模改修がされてない中で老朽化は進んでおり、統廃合もありうる状況下で今後1校当たり約8000万円と言う金額をかけてまで改修をしていくのか、と言う疑問が付きまといます。
昨今の酷暑の中で思うような水泳授業が出来ていません。
10時限といったコマ数をこなすために授業を組み替えながら消化しているのが現状です。
それには子ども達や保護者も振り回されます。
プールの管理では先生方の負担も重くのしかかります。
プールの清掃、消毒といった衛生面での管理や水の出し入れといった作業です。
水の止め忘れで管理者がかなりの賠償額を負わされた事案もあり、昨年の7月には文科省やスポーツ庁から各都道府県や指定都市の教育委員会教育長宛てに「学校における働き方改革に配慮した学校プールの管理の在り方について」という依頼文書が発出されました。
そういった経緯も伝え、先ずは子どもの泳力の向上を最優先に考え、先生方の働き方の改善を訴えました。
他の自治体では既に民間の水泳プールを活用しながら、インストラクターに指導をしてもらい満足のいく授業が年間通じて受けられている報告が各方面でされています。
本市は一つ民間スイミングスクールがありますが、営業の観点から受け入れる余裕はなく、また一つだけでは到底間に合いません。
市域が狭いことから子ども達をバスでの送迎をすれば良いと思いますが、問題は現市民プールを屋内型温水プールに建て替えられるかです。
前述したように寿命が近づいてきていますが、隣の堺市のプールが昨年閉鎖されたことから利用客が流れてきています。
その結果入場者数がかなり伸びているところ、市長答弁でも指定管理者と相談して維持管理を続けるという説明がありましたが、市民プールは利用者がファミリー層に集中し、開園期間が2カ月に限定されていることから、高齢者の健康増進も図れ、年間通じて利用できるものに思い切って立て直すべきと訴えました。今の場所は高圧線があり高さ制限があるので別の場所に立て直すべきです。
立地に適した場所はある程度想定されるのですが、これはまだ利用できるかどうか現時点では分からないこともあり、こちらから特定したことは言えないものの、時間が経ってからでは遅いと思いまして「使用済み紙おむつの燃料化事業」という提案を今定例会で行いました。
2020年、「使用済み紙おむつの再生利用」ということを環境省がガイドラインを策定し、自治体をバックアップして進めています。
大阪関西万博でも回収ボックスを授乳室に設け、それを新たな製品に作り替えるアップサイクルを皆さんに知ってもらおうという取組をされています。
本市では使用済み紙おむつを「熱利用」することによって、温水にする熱源に利用すれば、LPガスの使用量を抑えられます。
そもそも使用済み紙おむつは一旦燃えだすとかなりの熱が上がるのですが、焼却炉を傷める原因にも繋がり寿命を縮めてしまいます。
つまり多額の税を投入してまで炉の改修工事を早めなくてはなりません。
年々高齢者の紙おむつの使用が増え、事業系可燃ごみは横ばいか増える傾向にあります。
また、もともと水分を多く含んでいるので焼却残差が多く残ります。
清掃工場で焼却処理をせずに燃料化装置で処理をすれば、燃やさずに済ませることが出来るのでCO2削減につながり、地球環境にも優しい取り組みをする自治体としてアピールできます。
ましてやペレットにして保存しておけば、災害時にもお湯を沸かせたりといった利用も可能です。
高齢者施設や保育園と言った福祉施設から排出される事業系可燃ごみが減れば各事業者の負担も減り、利用者の負担軽減にも繋がるものと思われます。
こういった資源の好循環が社会の健全性を生み出し、環境教育に繋がることが未来への確かな投資になることは間違いありません。
市長からは、要約すると「先の話ではあるが一つの提案として受け止め関係課職員で検討していく。教育の抱える課題や市民プールの抱える課題はリンクしていることから今後の在り方を含めた中で施設の寿命の先を見据えながら関係各課を含めて検討チームを立ち上げる。その中で民間の資金やノウハウ、運営や維持管理まで含めた中での提案をいただけるようなところを今から研究していくように両副市長には指示を出している。今後の在り方については非常に大きな課題であるので研究検討を今後スピードを持って取り組んでいく。」との熱い答弁をいただきました。
是非ともタイミングを逸することなく適切な判断をお願いしたいと思います。
2025年8月20日 | 活動報告
本日は公共施設特別講座2日目。

③10:00~12:30
『公共施設更新費用と財政的な視点』
④13:30~16:00
『インフラ老朽化の課題』
③では財政を専門とする財政的な視点からの説明で始まり、国費や地方債の考え方については元財政課職員でしたのでよく理解は出来ました。
国の制度や予算をどう活用するかによって今と後年度の負担がかなり変わってきます。
それに加えてどの起債の種類があたるかによっては交付税参入があるか無しかで財政的な負担も変わります。
等級化した施設の更新に関してはどの自治体も悩ましい問題です。
予防保全の観点から長寿命化をして活用し続けることが基本的な考え方になると思いますが、人口減少に伴い全体的な送料の抑制も考えないと維持修繕にかかる費用は増えるばかりです。ましてや利用者の事も考えると例え公共施設であろうとランニングコストを賄える収支見通しを立てないと赤字の垂れ流しでは立ち行かなくなります。
公共施設の集約化・複合化も視野に入れながらこれからの住民ニーズに合った公共施設の在り方を今から研究検討していかないと取り敢えずの延命治療だけではツケを後年度に回すだけだと思います。
④では主に自治体が担う土木関係の投資の更新時期を迎えるにあたり、その中でも道路、上下水道菅、橋梁など老朽化によって全国的に事故が生じている事例も交えながら対応の必要性を学びました。
本市は平地で面積も小さい自治体であることから、あらゆる面において効率的に税の活用をすることが出来ています。
基幹管路の耐震化も100%達成し、災害時にも住民の暮らしを守ることを第一優先で市政を進めて頂いています。
早くから進めた下水道も普及率が高く、衛生的にも安全性にも優れた街並みが実現していますが、老朽化した下水道管の更新も今後必要となっています。
そのような状況において全国的に技術系職員の採用問題を抱え、今後益々必要性が高まる職員の不足が課題となっています。
小規模自治体では職員の数も不足していて、土木と建築のそれぞれの分野のバランスの整った職員体制は望めない中での市政運営の舵取りは非常に難しいものと感じました。
必要な人材を自前で育てる発想もこれからは必要な時代なのかと思ったりもします。
自治体職員がかなり転職等で流動的になってきている昨今、働き甲斐の有る職場づくりにも傾注しなければならないと改めて感じた次第です。
2025年8月20日 | 活動報告
今朝は6時15分新大阪駅発東京駅行きの新幹線に乗り込んで、新宿にある会場で10時からの公共施設特別講座を受けました。
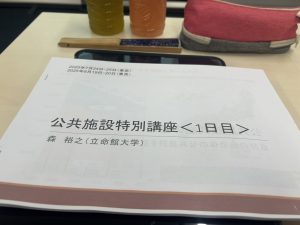
①10:00~12:30
『公共施設問題の基礎』
②13:30~16:00
『学校統廃合と公共施設問題』
議会で配られた地方議員研究会が主催する講座案内チラシのこのテーマに目が留まり、直ぐに申し込みました。
本市でも全国の潮流にあるように公共施設の今後の適切な維持管理が問われています。
人口減少社会であり高齢化を迎え、公共施設をこのまま維持管理していくことの問題点を講師の立命館大学政策科学部の森教授から説明され、今後住民にかかる負担が重くなるのは必至です。
人口急増時代に増えた公共施設の一人当たりの延べ床面積をどう減らしていくか、どの自治体とも大きな課題がのしかかります。
①の基礎講座では財政的な見地からこのままでいくことの適当なサービス配分が可能かどうかの問題点を分かりやすく教えて頂きました。
適切な公共施設のマネジメントをしなければ、維持管理費に予算が費やされ、一般財源等を他の政策に振り向けることが出来なくなります。
参加されている議会の一部の状況を分析しつつ、先進的に取り組んでいる自治体の事例をもとに講義が進みました。
公共施設の整理の仕方について何が正解で不正解かはありません。
その土地土地の課題は様々で、色んなケースを知ることで引き出しを多く持つことが肝要なのだと学びました。
②では特に公共施設の延べ床面積の多くを占める教育施設をどのように縮小方向へ導くか。
アプローチの仕方や環境が違う中で、松原市にあった考え方を見つけていかなくてはいけないですが、一体誰が絵を描き推進していくのか。
地元から上がっていくことが最も円滑に進むような気もしますが、地域を巻き込んでの統廃合するパワーは想像を絶するものだと想像します。
講師からは、廃校する側の学校の利用も同時に考えないと上手くいかないとの貴重な見解をお聴きし、地域ごとの合意の下で統廃合を進めなければならないのなら、そう簡単には物事が進まないことを改めて思い知らされる研修第1日目となりました。
建設すること以上に整理することの理屈をどう住民に理解して貰えるかが重要となります。
良いものに建て替えることが出来れば住民の理解も進みやすいですが、ただ単に無くすということはかなりの説明責任が必要です。
市政を担うリーダーとして決断することが求められますが、政治家としては出来るならば避けたい分野であることも事実です。
しかしながら先延ばしすることによって、今後益々多様化する住民サービスの質と量を狭めないように注力しなければその自治体の明るい未来は開けないこともまた事実だと思います。