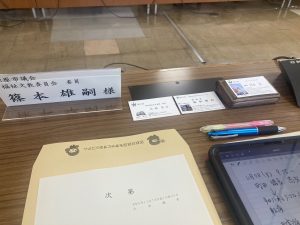2023年12月7日 | 活動報告
令和5年12月6日(水)
今回はこれまで疑問に思っている公共施設循環バス(ぐるりん号)の問題と少子高齢化から来る問題を抱えている2つのテーマについて質問しました
1.防災教育について 1.これまでの取組みと本市中学生に今後期待すること
きっかけは東京都荒川区の中学生の防災部の記事を見つけたことでした。
本市でも避難所運営マニュアル作りや避難訓練に中学生の関りを持ち始めてくれ、災害時には立派に活躍してくれている姿を見て、是非とも防災部を本市でも作れないかと言う提案をすることが目的でした。しかしながら今の防災教育を通じて、またインターナショナルセーフスクールの取り組みを通じて主体的に動ける訓練が出来つつあり、また母校の中学校では防災をテーマに、各中学校にある「人権サークル」が活動をしている中で、先日の中学校フェスタで生き生きと活躍している姿を見て、ひょっとしたら本市の中学生の方が進んでいるのかも、と思ったりしたほどでした。
まだ全中学校に広まっていないので、それを是非広めてもらって、災害時には中学生が活躍して貰える環境を作ってもらうことをお願いしました。
視察先の荒川区は東日本大震災の被災地との交流を毎年持っており、その点については本市も出来たらもっと意識が高まると感じました。
「助けられる人から助ける人に」これは私がかつて避難所運営に関わった時に実感したこと。
これは共通のコンセプトでした。
冒頭あいさつの時に荒川区議会議長さんが言っておられたのは、「助けられる大きなこどもではなく、助ける小さな大人への転換」が必要とのことでした。
目から鱗が落ちる一言でした。
本市も中学生がこれからの防災リーダーとして、また地域のリーダーとして活躍してくれることを期待します。
2.ぐるりん号について 1.2024年問題をどう捉えているか
平成11年度から市民の足として無料で運行している公共施設循環バス。
主に移動手段を持たない高齢者の足として、通院や買い物に利用されている。
数年前には、このぐるりん号の運行について疑問を持ったことから、代替え公共交通を真剣に考え、京丹後市まで視察もしたりしました。
オンデマンドバスが走る地域もちらほら出てきている自治体の情報も仕入れながら、担当課職員に色々と研究もしてもらいました。
結果は完全なるオンデマンドバスへの転換は難しいとのこと。地域の公共交通とのバランスが問題となる、と回答でした。
いったん断念はしましたが、昨今のドライバー不足と2024年問題から本市もドライバーの確保に今後悩むされる時が来るだろうから、今から地元の公共交通を活用して、なおかつ市民が喜び、市にもメリットがあるやり方への転換を図ることを研究しておくように要望しました。
時代の流れによって四半世紀前に始めた住民サービスのやり方が継続していけるとは限らない。
これ以上委託料の増額はありえないし、市外の観光バス会社に高い委託料を払うことよりも、市内の事業者を活用することをもっと意識しなければいけないと思います。
三方良しの施策を展開して貰うことを望みます。
3.総合型地域スポーツクラブについて 1.当該スポーツクラブの現状と今後における本市にとっての必要性について
本市では平成20年に3つのスポーツクラブが創設されました。
国の施策で「競技スポーツ」だけでなく「生涯スポーツ」としてのスポーツあり方もすそ野を広げていかなくてはいかないとの考えから全国の8割近くの自治体で3500を超えるクラブが出来ました。
しかし、15年余りが経つ中で高齢化が進み、クラブの弱体化も進みました。
会費だけでやりくりしているクラブは運営が非常に苦しく、自治体からの施設の指定管理委託を受けていたりしている収入があれば良いようですが、全体から見れば僅かな割合です。
もともと自主的、主体的に活動する団体で、本市でもクラブと市との付き合いはありませんでした。
ここへ来て何とか自治体の支援が必要だと言うことが言われ始め、それを議会で訴えました。
公益性が強い団体がスポーツ行政の一翼を担ってきたことを評価して、高齢化した今の組織を立て直すことは難しいであろうことから、新たに参入したいというところを核として、スポーツ関係団体や周辺の大学とも連携し、市民の健康増進のため松原市のスポーツ行政をしっかりと進めて貰いたいと思います。
2023年11月9日 | 活動報告
本日、午後2時より標記協議会が開催され、議会選出委員として出席しました。
令和6年度から始まる松原市第4次障害者計画に基づく、「第7期松原市障害者福祉計画及び第3期松原市障害児福祉計画(素案)」について事務局から説明され、それに対しての質疑が行われました。
私が気になったのは、広く市民を対象に人権講座やイベント等の人権啓発活動をはじめ、教職員に対する人権研修等を積極的に進めたり、小中学校の児童生徒に対しては、出前講座で車椅子の体験学習等を通じて人権感覚を磨くための機会を提供している・・・との説明文がありながら、手帳所持者は障害があるがために差別や偏見を感じることの有無を問う設問で前回と今回を比較した結果では、有りの割合が増えており、所持者以外も障害者に対して差別や偏見が増えていると感じていることに矛盾を感じたところでした。
従って、何故そうなったのか分析が出来ているか質問しました。
事務局の説明では、人権に関する差別や偏見を勉強するほど知識が高まり、それに対する意識が増えた結果だと言うことでした。
と言うことは、知らない人が多いほど差別が無い社会だという結果になるのか。
ならば、知らない方が幸せな社会に近づくのか…
そうではないだろう。
手帳所持者からしても増えていることが説明できるか?
当事者は肌で感じているところなので、純粋に増えていることの原因は他にあるはず。
今後の課題とします。
2023年11月7日 | 活動報告


11月7日(火)午前10時~11時30分
東京都荒川区 区役所5階にて
「防災部の取組について」
視察二日目は東京都荒川区を訪れました。
中学生が防災に関わっていることに大変興味を持ち、今回の視察のテーマに採用頂きました。
本市では、松原防災士会が主となって、各関係団体と協力の下、市危機管理課の並々ならぬご尽力で市内小中学校22校全てで避難所運営マニュアルを策定しています。作ったマニュアルは防災訓練の際に見直すことをしているのですが、一部中学校で生徒が訓練に関与したことから、防災部創設と言う荒川区の取組に惹かれました。
南千住第二中学校のレスキュー部創設がきっかけとなり、区内全ての区立中学校に防災部が広がりました。
「助けられる側から助ける側に・・・」
この考え方は私が2019年10月末に台風21号が大阪を襲った際、もう少しで大和川が氾濫する一歩手前まで水位が上がり、避難勧告が出された時、避難所に居合わせた経験からそういう考え方を抱いたのでした。
それを基に防災士資格取得の補助制度を市に求め、市長が快諾。
それが松原防災士会の始まりとなります。
助ける側の人を増やさなければ、避難所は運営できないのです。
それを当時、私は骨身にしみました。
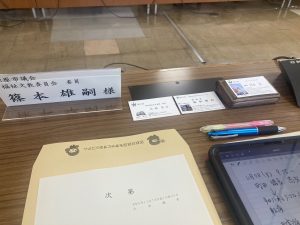
8年前、荒川区長も同じような思いで、防災部を全校に広めたとお聴きしまいた。
部創設後、他のクラブと兼務して入部できる環境の下全校生徒の約1割の生徒達が地域、消防団、自主防災組織などとの関りの中で知識や経験を積み、自助・共助を実践されています。
ジュニア防災検定も受け、90~95%の割合で合格しているとのこと。
この活動を通して中学生は人との接し方を学んだり、顔の見える関係を築いたりと、防災というテーマだけでなく、中学生自身が成長する中でとても大切なものを身に付けて行っているようです。
私が最も気になっていた、防災部出身の子達がどういう進路を辿っているかということ。
そこは荒川区さんも中学校を卒業すると関わりが持てなくなり、しっかりとした情報を掴めてないと説明されていて、とても残念でした。
こういう場合は、その検証方法を先に見据えて考えておいた方が良いのだと思いました。

その後、各議員からも種々質問が飛び、有意義な視察となりました。
お時間いただいた荒川区の皆さん、ありがとうございました。
2023年11月7日 | 活動報告


11月6日(月)午後2時~3時40分
東京都葛飾区 区議会棟にて
「民間の屋内プールを活用した水泳指導について」
令和4年第4回定例会にて「学校プールの今後の利用方針」について個人質問を行った。
学校の廃校の数を上回る学校プールの廃止のニュースを見たことがきっかけであった。
昨今の気象状況により、計画的にプールの授業がしにくくなった現状があり、屋内温水プールを利用する学校が増えてきている。
さらには老朽化による施設の更新、先生の働き方改革などが背景にある。
葛飾区では二つの総合スポーツセンターに10の民間施設(スイミングスクール)を活用し、予想以上に早いペースで屋内プール使用へと移行が進んでいる。
アンケートを実施しても先生、児童の殆どが屋内プール利用を良としている。
試算では1施設当たり2億数千万円かかり、現行とランニングコストを比較しても老朽化したプールを建て替えることは全ての面において
選択肢から外れることが容易に判断できる。
また、行財政改革の一環としても進めるべきだと私は以前から主張している。
学校給食の無償化が本格的に市単費で続けていくには財源がここで生まれると考える。
担当課長さんから資料に基づいて説明を頂き、私が考えた事前質問にもお答えいただいた上で各自から様々な側面から質問が出た。
私は最初に手をあげ、先ずは受け皿となる民間施設は快く受けてもらえたのかについてを伺った。
基本的に休館日を活用しているので施設側としてはかち合うことはなく、売り上げにも貢献しており、問題はないとのこと。
また、昔よりも水泳授業数が減っている中では泳げない子が増えてきていると予想されるが、インストラクターにグループ分け指導を受けられることで泳げる子が増えてきたのではないかと言う質問に対しては、やはり楽しく水泳が出来ることで自信がつき、上達するこが増える傾向にあり、また、見学をした保護者からも好評を得ているとのこと。

全ての学校が進めていくには受け皿に限界があるが、今後2箇所、学校授業を優先する施設を建設する予定だと言う。
議会からは民間に任せていては持続可能性の担保がとれないのでは?と懸念する声も出ているそうだが、そのあたりは受け皿となっている民間施設と調整していくことや新建設の施設を活用することで継続性が保てるとしている。
また一方、使わなくなった学校プールについても今後長期間放置も出来ないことから、これから費用対効果を鑑み、学校現場と財政当局と相談しながら、跡地利用についても消防水利を損なわないようにして進めていくとのこと。
事前に葛飾区が作成された資料で勉強していったが、現場で直接やり取りをすることで、やはり屋内温水プールを活用することに圧倒的な有利性は働いていると感じた。
問題は松原市に民間施設が一つしか無いというところ。
学校授業を優先できる施設を建設できれば、その問題は解決できるはずである。
公立15小学校のプールの建て替え問題がいずれ出てくるのであれば、早めに方針を立てるべきであると、今後も行政へ働きかけていくつもりである。
2023年10月3日 | 活動報告
9月29日から始まった決算特別委員会は10月3日までの3日間で審議が終了しました。
●9月29日(金)
一般会計の内、総務建設委員会所管の部署の事業に関する審査
①商店街・小売市場等魅力向上事業(産業振興課)
令和3年11月17日に天美東に「セブンパーク天美」がオープン。
出店計画時点から天美駅前の商店街の衰退は懸念されていたが、やはり予想以上に現実のものとなった。
その年の12月議会で、商店街も含めた活性化策を打たなければ商店街が危うくなると警鐘を鳴らし、令和4年度予算で「にぎわいづくり支援事業」がコンサル会社に委託された。
そもそも建設計画が進む中で契約委託先がいったん白紙になり、かつ契約先が変わった後、再起動してテナントが決まりかけていたのにコロナで撤退が余儀なくされ、タイミングが合悪いことが重なった。
そんな状況で、天美駅前の商店街からマクドナルドやスーパーのライフ、auショップなどがテナントとして移転した。
集客力の強い店舗が移転したことにより、駅前商店街の人通りは確実に減ったと言える。
それを盛り返すためにも行った事業だが、最終的には本当に使えるのか?と言った報告書だけが残った。
駅の乗降客は増えたと計画書にはあるが、その実感は地元民として感じない。
万博を見据え、市外からの訪問客も増やすためには、松原市駅前のホテルの稼働率やアンケートから見ても民泊などが成功する可能性があるのでリフォーム会社がカギを握ると見越している。また、地域住民の憩いの場を創設することによって、空き店舗の新たな利活用を図り、活性化につなげるといった内容である。
商業活性化・商店街活性化はかなり前からやっており、即時的にどうにかなるものではない。
継続して取り組んでいくべき問題であることは誰もが分かっている。
今回の約900万円という予算で得たものが妥当なものかであるが、これからの取組をしなければ単なるゴミになってしまう。
店主も地域も高齢化が進み家から出る機会も減り、若い世代はネットショップを利用するかショッピングモールで一日を過ごす。
こんな風景が当たり前になってきてもなお、商店街を大切にすることも大きく問われる中、これまで支えてきた街の灯を消して良いことにはつながらない。
地元市議として、また地元連合町会の現代表者として、10年先、20年先を見据えて時代の流れに逆らってでも行動していくことに全身全霊を捧げたいと思う。
②不法投棄等防止対策事業(環境業務課)
前年度比較をして不法投棄の回収が変わっていない所から調べ出し、ここ4年ほどそれほど変わっていないことに疑問を持ったことから質問を行った。
平成29年から不法投棄対策として、また行財政改革の一環として始めた「不燃物粗大ごみの電話申し込み制」。
松原市は昔から無料で回収しており、その為に近隣市からゴミが持ち込まれ、市民の税金で対応することに何とか対処しなければならないと行政が動き、功を奏してきた事業である。
ただ、ここに来てその回収量に減少が見られなかったことを質問すると、水路のスクリーンや天美ポンプ場に河川水路を流れてきたゴミなどが雑草などと混ざっており、分けて軽量できていないことからそのあたりの量が明確に出来ず、数年は量が一定しているとのこと。正味のところは月に2tぐらいで、どうしても防ぎきることが難しい不法投棄であると説明を受けた。148tというあまりにも不法投棄が多かった時に防犯カメラを付けだしたことが最も効果的な結果が出ており、平成25年度から右肩下がりに減少してきた。
市内全ての箇所に防犯カメラを設置することは現実的ではないし、ずっと見張っているわけにもいかない。
捨てられやすいステーション収集を戸別収集に変えていくことで地道に防ぐことしかないのではないかと思うのでそれを提案した。
現に以前、相談者から受けたのもその話。その時は市が直ぐ動いてくれ、住民から喜びの声を頂いた。
他所へ自分が出したごみを持っていくことの理不尽さを感じられないマナーや道徳のかけらもない人間がいる限り、不法投棄は無くならないだろうし、それに貴重な松原市の税金を使われることに釈然としない日々が続く。
③道路維持補修業務(みち・みどり整備課)
行政評価シートを確認すると、相談対応が100%出来ているとあった。
でも相談して、舗装の打ち直しが出来ていない箇所は結構ある。
何故なのかと言う疑問があった。
相談を受けて調査を行えば対応したとの見方をしている。
毎年の予算が限られており、最近は資材の高騰もあって中々進んでいないのではないかとも推察する中で、工夫をしながら発注をしているのも理解している。
毎年の補修の出来高が分かりづらいので数値化して比較できないかと聞いてみたが、種類があって比較が困難であると説明を受けた。
以前からこの事業に対してもう少し予算の拡充が出来ないかと担当者とも話してきた。
道路の経年劣化が進む中で、国の補助金が付かないことで率先して市も動きにくいが、やはり高齢化が進む中では少しの道路の傷みに躓いてこけるなどして寝たきりになると、本人はもとより、家族も大変な負担が強いられる。ましてや医療費の増大と言うことで保険者である自治体にもボディーブローが効いてくる。
そうならないためにも足元の安全対策を是非とも進めて貰いたいことを訴えた。
●10月2日(月)
一般会計の内、福祉文教委員会所管の部署の事業に関する審査
④まつばらテラス(輝)運営管理事業(高齢介護課)
「健康・学び・交流づくり」として子どもから元希者までさまざまな世代の人が利用できるにぎわいのある施設として、平成29年1月15日オープンしました。(市HPより抜粋)
オープンしてから市直営で管理運営してきた当該施設。約5年間の安定的な運営を目指してきたところからより効率的な運営へと切り替え、令和4年度から指定管理者による管理運営となっての効果を問うた。
委託先はミズノスポーツサービス(株)であり、これまでもオープン以来文化・運動プログラムを担ってきたことから、他の業務との効率性で今まで以上に効果的に利用者に向けたサービスが提供できているとのこと。
財政的な効果で言えば約900万円の委託料が、一括して取りまとめることにより削減できた。また、以前職員が一人張り付いていたことからすると0.3~0.5ぐらいの人員で済むとのことから、実質1000万円強の財政的効果があったと思われる。
また来館者数も増え、施設利用料やプログラムの参加料も増えたのと実績が見られている。
コロナ禍によって一時期はかなり減った来館者数もまた増加傾向にある。
利用者に親しまれる管理運営に今後とも努められたい。
⑤少年自然の家管理事業(いきがい学習課)
この事業については、本会議一般質問で行ったクリエート月ヶ瀬のテーマで時間がタイトであったため、聞けなかったというよりは言えなかったところを今回の決算審査で補った。
経費については事前に調べておいたが、敢えて建物の事態の管理について問うた。
地元業者に除草選定をしてもらってはいるが、令和4年度から老朽化を理由に閉め、その後の利活用を図っているにもかかわらず、老朽化を進めてしまう管理の仕方に疑問を持った。
建物を修理修繕して利活用しようとしている業者がおり、興味を持ってくれているのにこれ以上老朽化を進めては当初の計画から交代してしまい、計画を白紙にしてしまう。
市としては良い形で譲渡することが望まれるところ、この状態を放置しておけば、土地も建物も有効に活用できなくなってしまうと警鐘を鳴らしました。
副市長からは、市長からも早急に対処してくようにとの命も受けているので対応していきたいとの答弁もあり、活用したい事業者に早く引き継がれることを心から願っている。
⑥病児保育事業(子ども施設課)
令和4年度から病後児保育から病児保育に拡充された。子育てと就労の支援を目的にその実績等を問うた。
委託先は阪南中央病院。病気中の子どもの大変な時期を安心して預かってもらう体制を整える環境整備の為に、これまでの病後児保育事業の経費に上乗せされ、国府市が3分の一ずつ負担し合っての制度の範囲内で予算額を定めている。
令和4年度は登録者数は65人利用者は延べ71人。さほど多い印象ではないが、よっぽど預けるところが無い家庭へのセーフティネットの役割であるために、本来は乳幼児であるがために親や祖父母親戚に預かってもらうことが安心であり、その世帯が多いとの説明を受けて納得した。
今後益々、孤立化していく家庭が増えないとも言い切れない時代なので事業の継続を願うものである。
⑦児童・生徒理解活動(心の教育)推進事業(教育研修センター)
本会議一般質問で「教職員の働き方改革」について質問をした。
その改革の大きなポイントは「スクールカウンセラー(SC)」であり、「スクールソーシャルワーカー(SSW)」であると思う。
複雑な家庭が増えてきている中での生活面での問題、また様々な学校生活での悩み、子育ての悩み、教師としての指導の悩みなどなど、先生だけではとても対処できない事案が増えてきており、そこを担ってくれる職種であることは間違いが無い。
SSWは現在市に6人配置されており、この方達で相談を受け持って頂いている。
令和元年度は1,241件、2年度は1,862件、3年度は1,873件、4年度は2,234件。4年度の支援対象児童生徒数は625人。
ただし、中学校を卒業しても関わることはあると言うこと。
6人で約100人を超えるケースを抱え、今後も増えていくことが容易に想像できる。
これはSCに関しても同じであり、中学校では生徒・保護者・教職員で3,833人の相談があり、小学校では2,204人と伺った。
幼稚園では51人、教育支援センター「チャレンジルーム」では161人。4年度合計で6,249人の相談に実質11名のSCが対応している。
令和元年度は4,945人、2年度は4,998人、3年度は5,022人、4年度は6,249人の相談件数で年々こちらも増加している。
SCやSSWといった仕事は臨床心理士や社会福祉士、精神保健福祉士など資格を有している人が必要であり、もちろん経験年数も。
これから高齢者福祉や障がい者福祉などでも必要とされるこれらの有資格者を早めに確保しておかないと働き方改革にも影響が出る。
そのあたりを十分に認識頂き、子どもや親が安心して学校に通え、先生が元気に働ける環境づくりに努めて頂くことをお願いした。
●10月3日(火)
各企業・各特別会計の審査
終了後、討論採決が行われ、全会計の決算認定は承認されました。
2023年9月20日 | 活動報告
本日20日は一般質問二日目、トップバッターで個人質問を行いました。
◆質問通告内容について
①働き方改革について ①本市教職員の働き方改革について
②熱中症対策について ①本市公共施設(市民体育館)の空調設置について
③クリエート月ヶ瀬について ①クリエート月ヶ瀬が担ってきた役割と今後の利活用について
①働き方改革について ①本市教職員の働き方改革について
去る8月28日、現教職員の働き方は危機的な状況にあるとして、中央教育審議会の質の高い教師の確保特別部会から緊急的に取り組むべき施策を盛り込んだ提言を文部科学大臣に出されました。
教員を取り巻く環境は国の未来を左右しかねない危機的な状況にあるとして、国や自治体、学校に加え、保護者や地域住民、企業など社会全体で一丸となって課題に対応する必要があるとしています。
しかしながら、社会全体で一丸となるにもそれぞれに様々な課題がある中で、どういう風に松原市として教員の労働環境を良くしていくかをこの度の緊急提言に基づいて現場の声を聴きながら、また地域、保護者の声も聞きながら進めていかなくてはなりません。
先生が生き生きと働くことが出来、その姿から様々な刺激や影響を受けて育つ子ども達の未来のために、本市教育委員会として教職員の働き方改革について聞かせて頂いた。
この提言を踏まえ教師が教師としての業務に専念し、子どもたちに真正面から向き合うことができる環境を整え、単なる時短ではなく、児童生徒への指導の充実につなげていくことが必要だと考えているとの教育長答弁がありました。
まさしくそうだと思います。
時間外労働時間の短縮の向こう側にあるもの。子どもの笑顔なんだと思います。
疲労困憊の先生の顔を見ていても、子どもは明るく育ちません。元気に教壇に立つ先生の姿に、子ども達は刺激や影響を貰うわけです。
メンタルがやられ休んだり退職する先生の数が全国的に9年前よりも1.5倍になったとの調査があるが、松原市として極めて少ない数ですが、予備軍がいるはず。そこにしっかり目配りを出来る体制を取って頂くようにお願いしました。先生が休んでいては児童生徒は心配でしかありません。
松原市ではこれまで、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、学習支援員、生活介助員など専門人材を適正に配置してこられた。その結果、確かに先生方の時間外勤務が縮小されています。しかしながら、新しいことに挑戦していくこの働き方改革の折に、時間外労働を減らすことだけに目を向けていてはいけないと思う。増えても良いんだと思います。やがて、それは効率化され、改善へと繋がっていくと私は信じ、時間外勤務時間の短縮された数値だけを追い求めるのではなく、元気な先生がどれだけ増えたか、なんて指標を考えておくべきだと訴えました。
進めるにあたっては保護者や地域に丁寧に説明をして、子どものための働き方改革を実現させてほしいと思います!
②熱中症対策について ①本市公共施設(市民体育館)の空調設置について
これだけ暑い日が続くのは正直体験したことがあっただろうか…
殺人的暑さと言っても過言ではない。しかし、涼しい所でじっともしていられない。
先月、議会での視察があり、大阪狭山市立総合体育館を訪れました。アリーナ、サブアリーナ、武道室にはクボタ製の農業用ビニルハウスで使用するスポットエアコンが設置されていました。市長の公約で熱中症対策を進めていくという方針で、近年の猛暑から熱中症患者を出さないために昨年取り付けられました。10台で約3千万円。キュービクルの増設工事は必要なく、電気代も低額で抑えられているとのこと。
おまけに避難所指定していることから緊急防災減災事業債の起債を発行して普通交付税の参入もある。この起債は令和7年度までしか今のところ活用できない。本市市民体育館は指定避難所になっていないから、この起債は使えないが、それに関わらず、これだけ運動中止が求められる熱中症アラートが出されていれば、倒れる人が出る前に何とかしなければならないと思う。
市民体育館のアリーナを利用されている人からの要望があがり、今回の質問に加えました。
研究を進めるという市長の答弁があったが、本当に前に進めてもらい案件である。
③クリエート月ヶ瀬について ①クリエート月ヶ瀬が担ってきた役割と今後の利活用について
昭和62年に開設された、現奈良市月瀬地区にある「少年自然の家クリエート月ヶ瀬」であるが、老朽化に相まって新柄コロナウィルスの感染拡大で閉館をし、そもそもの需要自体も薄れてきた昨今、令和4年度から休止となっている。
市はサウンディング調査をしたものの辺鄙なところにあって、周りには観光資源もなく、おまけに施設な古いとあっては、関心を示す事業者も期待できない。しかしながら、現施設を使って修繕を施し、事業を展開したいと手を挙げて下さっている事業者もある。
しかし、市が次の展開に中々動寝嗅いでいるがために、更に老朽化が進めば全ての事業者は離れていってしまいかねない。
行き着くところは、松原市が数億かけて解体し、所有土地を売却できずに塩漬けになって負の遺産となることが見えている。
だから、スピード感をもって事業者に移管する手続きに入るように依頼した。
議場では時間も無かったので触れなかったが、ミイラ化した遺体が解体できずに困っている公共施設の屋上から見つかったとの報道もあった。クリエート月ヶ瀬が万が一犯罪の温床に繋がれば、市にとって大きなイメージダウンである。
急かすようであるが、これは急かさないといけない案件。
もたもたしていたら悪い結果しか残らず、処分に関して議会の承認を得られないだろう。
そこを懸念して今回は質問を行いました。