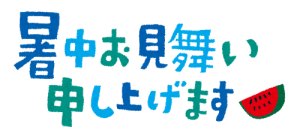2021年9月22日 | 活動報告
令和3年9月21日(火)午後11時30分 個人質問
「環境問題について 脱炭素社会を実現するために松原市として出来る方策は何か」
昨年の12月定例会の総務建設委員会協議会にて「地球温暖化対策~ゼロカーボンシティ~について」一般質問をしました。
脱炭素社会を実現するためにあらゆる課題に世界が立ち向かおうとしています。他人事では済まない状況が既に大規模災害という形で地球の各地で起こっています。
次世代に苦しみや悲しみを押し付けていいのか。
今、気ままに暮らした結果を子孫にツケを回しても良いはずがありません。
12月では「市の地球温暖化対策の推進に関する実行計画(第3次)」の内容と進捗度合いについて問いましたが、国に準拠した目標26%削減にはまだほど遠い状況です。
今年4月の地球温暖化対策推進本部にて2013年度比で46%CO2を削減すると菅総理が表明したことにって、いずれ松原市も準拠することになることが予想されますが、そのあたりの進め方や考え方がどのようなものか、今問わないといけない問題だと質問に至りました。
実際のところ、市の中だけの取組みばかりで、啓発活動や市民や事業者を巻き込んでの施策が十分に出来ていません。これまでからエネファーム設置補助や生ごみ処理機購入補助はありましたが、一部の対象者のみで効果検証も出来ていないのが現状です。
現状の把握と分析をしてこそ、今後の目標が立てられます。
公共施設には太陽光パネルを設置したり、地中熱を利用して光熱水費を節減し、CO2削減に努めておられるが、市内でどれくらいの太陽光パネルが設置され、今後のポテンシャルはどれだけあるのかなど、基本的なデータから抑えていかなくてはなりません。
やみくもに制度を作ったところで、それがどれだけCO2削減に貢献できているのか、またどれだけ市民や事業所に働きかけていかなくてはいけないのか分かりません。
先ずは足元の数字を抑え、インセンティブを持たした制度の確立を提案しました。
・太陽光パネルや蓄電池の設置補助
(国の補助制度の上乗せ 主に電気代半額キャッシュバック)
・企業への環境配慮型設備投資に対する補助
また、市でも再生可能エネルギーを生み出す施策も不可能ではないと訴え、維持管理が非常に難しくなってきた松原市が所有する少年自然の家「クリエート月ヶ瀬」の今後の利活用に変え「バイオマス発電設備」を民間と協力して建設し、そのエネルギーを公共施設で利用するなど、グリーンエネルギーにも力を入れるよう提案しました。
省エネルギーの観点からは、市でペーパーレス会議を推進するとありますが、なかなか抜本的な紙の削減にはつながっておらず、ここにメスを入れないと仕事も効率が上がらないと指摘しました。現在部長級にはタブレットが配布されており、その階級の会議だけしかペーパーレス会議が出来ていません。課長級迄配布予定は立っており、その後は順次導入していくとのこと。議員も今秋にはタブレットが入り、極力紙でのやり取りを無くそうとしていますので、しっかり合わせて進めていただきたいと要望しました。
市民協働で進めないと達成困難な目標をクリア出来ないことから、茨木市のエコポイント制度を紹介しました。もう間もなく国においても環境省が主導してグリーンライフポイントが来年4月から始まるようです。
お金をかけずに市内事業者にも協力いただき、省エネ行動に関してポイントが付与され、貯まったら商品と交換といった、楽しみながらエコを意識して貰う事は非常に意義があると訴えました。
また、2018年後半、燃料税増税に対する市民の暴動がきっかけとしてフランスに端を発した「気候市民会議」なるものがヨーロッパに広がり、日本でも徐々に広がりを見せ始めています。
市民を無作為に抽出した会議体で、専門家を交え、気候問題に関わってもらい、気候変動対策を議論し、市へ提言を出してもらうといったことが行われています。本市でも考えてみてはどうかと提案しました。
最後に資源循環の観点では、今問題になっている廃プラスチックごみの問題が重くのしかかってきています。
海洋プラスチックの問題が世間で騒がれ、何とかそのゴミを減らしていかないと2050年には魚の量よりもプラごみの量が上回ってしまうといったことも囁かれています。マイクロプラスチックが体内に入り込んだ魚を食べることで人間の体内にも蓄積が始まっていると豪州の研究チームが発表をしています。
既に環境破壊から健康破壊は始まっていると思っても良いぐらいです。
中国や東南アジアを中心とした国々が、プラスチックごみを輸入して、石油系燃料よりも安くつくからと燃料として活用していたが、分別レベルが低いためにリサイクルできないゴミも多く、それが放置されたことにより海洋プラスチックなど環境問題に繋がってきていたことから日本やアメリカなどからの輸入を近年禁止することとなった。
それは日本で年間に排出されるやう900万トンのプラスチックごみの15%を占めていた為、今では国内で滞留していると考えられる。
それをどう処理していくかという問題と直面している。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が今年制定、来年施行されるが、先ずは減らすことを基本として、プラスチック製品の合理的使用、長期間使用、過剰使用の抑制、再資源化されたものの使用努力が定められている。日本では「サーマルリサイクル」といった海外にはない考え方があり、年間排出量の58%が熱利用され、その熱で温水を沸かしたり、発電した電気を売電したりと清掃工場の活用も進んできた。
そのプラスチック製品の中でも資源ごみとして回収されることの多い、ペットボトルのリサイクル率を高めようとする動きが活発になってきており、飲料メーカーが頑張っている。
現在本市では、資源ごみとして缶ビンと一緒に回収され、業者で分別されたのち、再生処理工場に送られたりするが、飲料関係会社が直接きれいなペットボトルを住民から直接回収し、再生処理業者に売った代金と回収代金との差額を地域コミュニティに還元する仕組みを導入している大阪市の例を挙げ、本市でも取り組みを提案した。
これはペットボトルの水平リサイクルと言い、石油由来の原料から出来るバージンペットボトルと比較して、60%のCO2が削減できると試算されている。これほど効果的な事はないし、迷うこともない。
地域コミュニティとしても活動原資が少なくても振り込まれるのであれば反対の余地もないはず。
直ぐにその仕組みを導入してもらいたい。
以上、提案や要望が多く、片道30分の質問時間はあっという間に尽きてしまったが、市長には出来ることから進めていくと力強い言葉も戴いた。
松原市は非常に緑が少ないことからCO2の吸収源が皆無に等しい。
また、高速道路の結節点であることから、毎日毎日多くの自動車が松原市内を行き来する。
そんな地理的条件のもと、一日でも早く、「ゼロカーボンシティ」を宣言し、シティプロモーションも兼ねたこの取り組みをしっかりと前に進めてほしいと強く願うところです。
2021年8月3日 | 活動報告, 活動報告チラシ
2021活動報告チラシ(夏号)
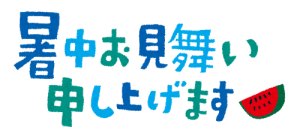

連日、酷暑が続きますが、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか・・・
コロナウイルス感染の第5波が襲ってきて、8月2日から大阪では4度目の緊急事態宣言が発出されました。
再び不要不急の外出が規制され、酒類を提供する飲食店の休業要請が出されました。
知り合いのお店はウンザリされながらも、決まりを守る選択を取られ、昨日からシャッターを閉められています。ゴールドステッカーを取得している意味合いがないではないかという声も上がっているのは確かです。忠実に守るお店がシャッターを閉め、生活に支障をきたしている一方、守っていないお店が売上げをひそかに伸ばすというニュースも聞いたりしますと世の中の矛盾さに辟易とするのは私だけではないと思います。
オリンピックやパラリンピックがせめてもの喜びであるかのように日頃は真剣にスポーツ観戦などはしない方ですが、メダルをかけて、また威信をかけて頑張っている姿に目頭が熱くなります。
昨日は野球が宿敵アメリカに逆転勝ちをおさめ、とても充実した思いに浸ることが出来ましたが、やはりコロナ関連のニュースを見るとデルタ株の猛威に自粛生活が長引く事も覚悟しなくてはと気持ちの浮き沈みに悩まされます。
ワクチン接種についてもデルタ株には有効でない確率がぐっと上がるというデータを見ると、今打っているのは意味が無いのではないかとさえ思ってしまいます。
政府はオリンピックの盛り上がりでこの局面を乗り切って、今秋の総選挙に臨めたらと微かな期待を寄せていたのではないかと思います。しかしながら、選手の間からも感染者が増え、その目算もデルタ株の勢いで消し飛ばされそうです。
純粋に競技が楽しめる状況にない雰囲気の中、懸命にメダルに向けて頑張っておられる選手の皆さんの心境はいかほどかと察するばかりです。
非難を浴びてまで続けていいのだろうか・・・などとこれまで人生をかけてやってきた競技、そしてメダルが誇りに思えないようにならないことを切に祈るばかりです。
疲れ果てた毎日に清涼と希望を与えてくれるオリパラを、開催地の国民として純粋な気持ちで応援しようではありませんか!
2021年7月7日 | 活動報告
7月7日(水)午前11時議会運営委員会開会
〃 午後1時本会議開会
各常任委員会委員長から各委員会での審査報告を受け、採決が図られました。
議案第36号と第37号について、日本共産党の反対があり、討論が行われました。私が会派代表で賛成討論を行い、委員会・本会議とも挙手採決がなされ賛成多数で可決されました。
次は追加議案があり人事案件について審議されました。
議案第41号では「副市長の選任について」ということで審議されました。新たに副市長が大阪府より招聘されました。今後松原市政の要として頑張っていただくことになります。議案質疑がされ、2名体制に戻した理由、大阪府より人を出して貰った理由やメリット、本人に期待するところ、などに対して市長が直接説明し、可決されることとなりました。
その他意見書の提出があり、我が会派からも提出した意見書は全会一致を見て、可決されることとなりました。
各案件の議決結果については以下のとおり
https://www.city.matsubara.lg.jp/material/files/group/51/reiwa3nenndai2kaiteireikaigiketukeltuka.pdf
2021年6月27日 | 活動報告
令和3年6月25日(金)午後1時より 本会議場にて代表質問第1日目
午前中の公明党の代表質問に続き、午後最初に自民党から代表質問に立ちました。
3月議会でも市長の施政方針演説に対し、今回は市長の選挙後に行う所信表明演説に対する代表質問となりました。
質問のやり取りについては以下に詳細を・・・
❶1.ポストコロナを見据えて
1.成熟期を迎えた4期目のスタートに伴い、各財政指標を注視しつつ、今後の収支
見通しを踏まえた中長期計画策定について
これまで市は行財政改革を断行し、歳入確保と歳出抑制を進め、健全と判断できる行財政運営を行ってきており、収支見通しを立て、中長期財政計画を策定することはしてきませんでした。
その理由は過去、財政緊急事態宣言を発出し、それが結果以上に厳しく想定していた、逆に言えば財政を悪く見せかけすぎていたということで議会から叩かれたことがトラウマになっているようです。その時は不確定要素があることを前提にしていたはずなんですが・・・
現在は、決算は勿論黒字であり、財政健全化指標は改善傾向にあります。市街化調整区域に大きな商業施設やその他企業の進出が決まっており、まちづくりが進むことで様々な収入が入っている予定になっています。
収支見通しを財政状況が悪化してからでは遅い。安定しているときに時点修正を常にかけながら市内外に向けてオープンにすることが、これからシティプロモーションを進めていこうとするならば一つの基礎資料になります。
一つ一つの良い要因悪い要因を線でつなぎ、収支見通しを立てる必要があると思います。
財政担当課も「財政運営計画」は大阪府への説明資料に毎年作成していますが、もっと洗練されたものを作ることで職員のスキルアップになることは間違いないこと。様々な資料を基に作成することになるので簡単にいかないのは私も経験者なので良く理解をしています。
かつて小泉内閣の時、三位一体の改革でかなり自治体の財政状況が厳しくなり、平成16年に収支見通しを作成した後、それきりになっていますが、技術の継承が途絶えかけています。
コロナ禍で策定するのは難しいでしょうが、最初は荒いものでも徐々に洗練されていけばいいことです。市からは「歳入・歳出に不透明な部分が多い事から、財政収支の推計には慎重を期す必要があり、今後、本市総合計画や各種計画との整合性を図りながら研究してまいります」との回答にはなりましたが、平成29年度決算委員会で要望してから、すっと言い続けています。今から準備してちょうどいい頃合いだと思います。是非、準備をはじめて貰いたいと思います。
❷ 2.第2期松原伊まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき若者世代の定住・移住を
促進するためにするべきこと
昨年度、市が策定した「第2期松原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」は20から39歳までの若者に軸足を置いた戦略を進めました。そのことに対し具体的にどうしていくのか・・・
リサーチが必要ということで市は最近毎年春先に転入出の理由のアンケートを取っている。
転入出の理由を聞いている項目に戦略を練る材料としての内容が含まれていないのは全く意味が無い。
仕事、学業、親からの独立などなど・・・
そんな項目しかないとどんな施策が功を奏しているのか分からないままである。
アンケートの項目とやり方を変えるように提案しました。受付で待っている間にQRコードから入ってウェブアンケートで簡単に回答出来、なおかつ協力者に対し御礼をすれば回答率も上がり、有益な情報が得られるはず。これはあくまでも転出者に使える選択項目。転入を促進する市外の若者世代がそもそも施策に興味があるはずはなく、ただ、転出する若者世代には具体的な施策のうち何が良かったか?などと具体的な選択肢があれば有益な情報が得られる。
一方、転入者には松原市のイメージを尋ねる。
市に求めるものを聞けば、市のイメージをどう変えれば若者が集まるかの戦略を練るデータが得られる。
地方に住みたい若者は「自然環境が良い」という理由が大きいと、日本財団が昨年17から19歳に向けたインターネット調査を実施し、1000人の答えから分析を行った。残りの項目は利便性、治安、育った場所だからとなっていた。
本市では「安心安全の取り組み」を進め、「利便性の面」では優位性があるとみるが、「育った場所だから」という理由が物語っているのは「町への愛着」そのものであるが、そこは疑問が残る。
早い頃から市外へ学校に通うと自分が住む市のことは知らず、愛着がわかないのは当然。
最近早くから私立等の学校に通う子どもが松原市には多い気がする。我が子もそうだが・・・
松原市のことなどに関心はない。家と学校との交通は電車故に松原の地理は何も知らない。
こんなことだから愛着が湧くはずもない。市立の学校の学力向上が無ければ出来る人材は流出するばかり。
結果、申し上げたのは、「自然環境」や「公教育」のイメージを上げること。それは自然環境である松原市に最も欠けている物である「緑」。それとこれまでからずっと低迷している「学力」。
ここを重点的にしていくと若者世代へのアピールになると私は申し上げた。
また、流出防止には市民満足度を上げることも大切。全て出来るはずはないが、しっかりとリサーチをしないとやみくもに市政を進めても空回りとなる。
市の看板政策であるセーフコミュニティやインターナショナルセーフスクールは若者世代にどう響くのか。市は肯定的な答弁をするが特にそれは否定はしない。そんな人も少なくても居るのは間違いないだろう。しかし、もっと若者世代にどうアプローチするか知恵を出し合ってほしい。
❸2.学力を伸ばす教育施策
1.本市の情報教育のこれまでの振り返りと今後の方針
2.GIGAスクール構想を本市で展開するにあたり、タブレットパソコンをどう生かし
ていくのか
今回のこの質問では私が平成14年度から平成17年度あたりまで財政課職員として教育費を担当していたことに起因する。
当時、国の事業でパソコンが市内各小中学校に配備が進み、その国の事業終了後も市単費で情報教育を推進したことでかなり多額な税金がこれまで投入されてきた。総額は今では30億円を超える。一度導入すれば途中で止めることは出来ない。しかしながら、その使い方について疑問を持っていた為、平成27年12月議会で質問した。当時の高坂教育長や高橋教育監から説明を受けたが、まだ疑念が払拭されたわけではなかったが、今回の質問にあたり調べてみると平成11年頃からの「情報教育推進協議会」なるものが、市内各学校の代表者が集まり、本市の情報教育についての指導方法を種々検討されてきたノウハウがそこに積み上がっているという。従って、この度のコロナ禍で一気に進んだ一人一台タブレットパソコンがいち早く導入が進み、基盤整備も進んできた経緯がある。端末の選定やこれまでの情報教育が有効に生かされるにはどうすればよいか・・・
そういったこれまでの情報教育とギガスクール構想との連動性がベースにあるのかどうかを確認し、また、多額の税金が投入されたことの費用対効果は子ども達にどう出ているのかどうか、総括をした上でないとギガスクールが生かしきれないことがあってはこれまでのアドバンテージが無駄になる。そんな思いで今回の質問に望んだ。
使い方としては年代に応じた情報リテラシーの習得に加え、授業をより深めるためのツールとしても使用していたとのこと。年間の使用時数は把握しきれていないが、1教室を全学年で共有していたのであるから、そういう面でそれ程使用頻度は上がっていなかったのかもしれない。数年前から各学校にタブレットが順次配備されるようになり、授業の仕方も変わっていった。
平成28年12月の本会議では、三重県松阪市三雲中学校の国の事業で一人一台タブレットが整備され、生徒一人ひとりの習熟度が即座に把握でき、持ち帰って復習させたりといったことができたので全国学テの平均点が上がったとの事例を紹介した。その時はまだまだギガスクール構想がやってこようとは思いもよらなかったが、この機会が訪れたことによって再度その事例を出し、大阪市で失敗したオンライン授業に軸を置くのではなく、理解度を深めることと児童生徒間の交流の充実に向けタブレットパソコンを活用して貰うようお願いをした。
また、今後5年以降は新たな更新経費がかかると予想されることから、現在のパソコン教室の在り方を見直し、その財源に不必要なもののリース代は直ぐに打ち切る必要があると促した。グーグルドキュメントとWindowsとの互換性においては戸惑うことなないと横田部長からの答弁にあったことから、クロームブックに特化してしまっても良いと判断する。
情報教育では当時先端を言っていた松原市。あまり巷や保護者の間では知られていないように見受けられるが、これまでの知識やスキルを無駄にせず、何歩も先を行くギガスクール構想を実現してもらいたい。
❹3.コロナ対策について
1.市内法人に対する支援策創設等について(中田議員関連質問)
❺4.スマートシティの実現について
1.行政におけるデジタルトランスフォーメーションの推進等について
(中田議員関連質問)
2021年6月19日 | 活動報告
令和3年6月18日
久しぶりの投稿になります。
5月の市長選挙後最初の定例会が開会されました。
5月16日の市長選挙では対抗馬が出ず、澤井現市長の再選が確定したことを受け、これまでの相談業務や要望活動はプライバシー観点から投稿は控えておりましたが、ようやく議会報告として投稿を致します。
今回は市長の4期目最初の議会ということもあり、所信表明が行われました。
3月の予算を決める大切な定例会では幹事長として代表質問に立ち、市長に対し、これまでの総括から展望を質問しました。
今回も引き続き代表質問を行いますが、骨格予算ではなく肉付け予算が既にスタートしていることから、ボリュームが少ないこともあり、一問一問をゆっくりとやり取りしたいと思っています。25日(金)2番目が私の出番ですので、議会生中継をご覧いただけたら幸いです(#^^#)
さて、今定例会で上程されているのは予算関係7件、条例関係7件。
❶報告第3号 令和2年度松原市一般会計補正予算(第15号)専決処分の承認を求めることについて
❷報告第4号 令和2年度松原市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)専決処分の承認を求めることについて
❸報告第5号 令和2年度松原市下水道事業会計補正予算(第1号)専決処分の承認を求めることについて
❹報告第6号 令和2年度松原市下水道事業会計補正予算(第1号)専決処分の承認を求めることについて
❺報告第7号 松原市市税条例の一部を改正する条例 専決処分の承認を求めることについて
❻報告第8号 松原市都市計画税条例の一部を改正する条例 専決処分の承認を求めることについて
❼報告第9号 令和3年度松原市一般会計補正予算(第3号)専決処分の承認を求めることについて
❽報告第10号 令和3年度松原市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)専決処分の承認を求めることについて
❾議案第35号 令和3年度松原市一般会計補正予算(第4号)
❿議案第36号 松原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号等の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定について
⓫議案第37号 松原市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について
⓬議案第38号 松原市印鑑条例の一部を改正する条例制定について
⓭議案第39号 松原市定数料条例の一部を改正する条例制定について
⓮議案第40号 松原市移動等円滑化のために必要な道路及び特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について
以上の議案説明、並びに議案質疑が行われ、約2時間の議会の初日は終わりました。
今回の議案の中で特に印象があるのは、コロナ禍で影響が大きく出ている飲食店に対する救済制度。4月25日からの緊急事態宣言発出に伴い、完全に休業を強いられた飲食店を応援することが今求められているとの考え方に基づいて、新たにテイクアウトやデリバリー等を始めた事業者に対し、対象経費10万円を上限に補助をするということ、また感染症予防対策を施す飲食店に対し、5万円を上限にその諸経費を補助。そして、雇用を確保するために事業者に対し府の制度に横出しで補助をするなど、コロナでまだまだ苦しい事業者と市民救済に向けた予算が計上されている。
今は国からの交付金を基に考えられているが、コロナが終われば各基礎自治体が自分の足で立って進まなければならない。
国の借金返済が始まると各自治体への対応が厳しくなると予想される。
足腰の強い財政基盤を今から作っておくことが大切である。
次の25日の代表質問まで担当課とのヒアリングが続く・・・
2021年3月27日 | 活動報告
26日(金)午前11時 議会運営委員会開会
昼からの本会議の議事の進行について確認を行った。
詳しくは議事日程の確認、討論者の確認、採決の図り方、休会中の委員会調査、第2回定例会日程案などについて話し合われました。
同 午後1時 議会開会
開会後、予算特別委員長、福祉文教委員長、総務建設委員長の順番で委員会の審議結果について報告がなされた。
条例案1件、予算案4件について委員会で討論され可決となった案件については、再度議場で反対・賛成討論がなされます、結果いずれも可決となり、最終的には市から提案された議案に対しては全て可決、承認、同意することに決しました。
議会議案も3件あり、提案理由をそれぞれの会派代表が説明し、私も担当致しました。
➡詳細は広報まつばら5月号をご覧ください。
令和3年度当初予算については、5月に市長選挙を控えながらも通常予算が上程されましたが、過去、前市長の選挙の折には骨格予算を組み、当選後政策を明確に打ち出すために肉付け予算が組まれたと記憶しています。
市民の経常的な市民サービスは空白を開けられないので当初予算で組み、政策に関する予算については選挙後に肉付けの補正予算を編成しますが、4期目を迎えるにあたってもこれまで通り、現市長の考えのもと通常予算が上程されました。私は過去財政課職員として骨格・肉付け予算の編成を経験したことがあります。これはこれで手間がかかりますが、予算編成の手続きとしては当然のやり方も現在の財政担当職員は知っておかなくてはなりません。
今回の定例会において、もっとも高い市民の関心は、30%のプレミアムが付いた商品券事業でしょう。これまで市は3回(国の消費税増税に絡む低所得者対策として実施分も含む)やってきており、また高齢者向けの商品券事業は毎年やっているので、かなりノウハウが蓄積されている。
しかしながら、今回はコロナ禍で販売方法がガラッと変わったので、不備も見られた。4月1日の補正予算の専決処分で委員会付託された質疑において、私が質問した結果、市長と意思確認が出来ておらず、一時混乱が生じた。これに関しては販売時の対応を変えることにしたが、想定どおりに行くか不安である。本日最終日は、今後この事業にはコロナ対応の交付金を充当する名目で、国からの指導で繰越できなかった販売事務費等に係る予算が、まだ始まってもいない令和3年度補正予算として上程されました(これは法的にも問題無いということで確認もしています)。これも可決はされましたが弱冠煮え切らない雰囲気の中、もともとコロナによる緊急経済対策によるもので、議会からも要望していた対策の一環として実施したこともあり、反対の声は上がりませんでした。