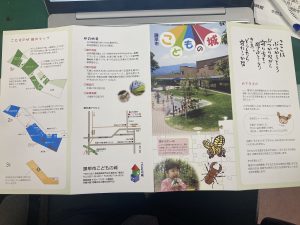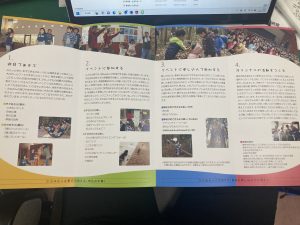2022年12月6日 | 活動報告
令和4年12月6日(火)午前9時登壇

◎今定例会の質問事項
1⃣公共施設について
①松原市のアセットマネジメントの進捗状況について
2⃣学校教育施設について
①校舎の大規模改造と長寿命化について
②学校プールの今後の利用方針と体育館の空調の必要性について
3⃣中学校の部活動について
①公立中学校における運動部活動の地域移行の提言に基づく市としての今後の方針について
・松原市のアセットマネジメントの進捗状況について
今年の3月議会において、各公共施設のライフサイクルコストの算出方法とその施設に係るより精度の高い予防保全に係る対策費用をどう見積もるかなどを問いに対し、庁内横断的に連携を取りながら全体的なマネジメントを取っていく体制を整えると共に、点検マニュアルによって職員研修を行い、スキルや知識の向上に努めているとの説明があったので、それが現時点で具体的にどのように進めておられるのかマネジメントシステムの内容も含めて質問をしました。それぞれの施設の構造や部材から耐用年数などを割り出し粗方の修繕計画が出され、その上で実際の傷み具合の状況を基に優先順位を付けて行きます。限りある予算の中で事後保全にならないようにひき続き予防保全に努めてもらうことをお願いし、東京都東村山市で取り組んでおられ、これまでも私が市に提案している「包括管理業務委託」の成果や効果について紹介して、今後の参考にしてもらうことをお願いしました。質の高い施設管理が出来るとしています。
・校舎の大規模改造と長寿命化について
平成27年度に策定した公共施設総合管理計画に続き、令和3年3月末で個別施設計画を策定し、人口減少時代へ突入している昨今、施設の老朽化も目立ち、今後の施設の在り方を検討していかなくてはなりません。
松原市内で約100施設存在し、公共施設の延べ床面積が28万㎡にも及びます。
その内、学校教育系施設が約58%(約16万㎡)もあり、大きな割合を占めています。
小中学校の校舎や体育館は昭和40年代当時の人口急増期に建てられ、50年前後の年が経過しています。
これまで年次的な大規模改造工事が進められてきましたが、令和5年度から国の方針が変わり、今後の改造工事はこれまでの原状回復から長寿命化を図ったものへと転換が求められます。つまりより大きな工事が求められる訳です。
しかし、少子化に伴って児童生徒数やクラス数が減少し続けることが予想される中、施設の適正配置、つまり統廃合の方針が決まっていない中で大きな投資をこれまで通りしていくやり方に疑問を持たざるを得なくなり、質問することになりました。
施設の計画は統廃合や複合化など一定の整理の方針を基にアセットマネジメントを進めるとしています。
ただ、その方針が定まっていなければ、計画としては完成されたものではなく、統廃合には校区審議会等を経て了承を得、首長の大きな決断と必要となることから、早期に方針を立てて長寿命化を図るべきと言う立場で訴えました。
・学校プールの今後の利用方針と体育館の空調の必要性について
全国的にプールを廃止し、共同運用や市営プール、民間プールを活用する動きが出てきています。
約1000校以上の公立小中学校が自治体独自のやり方で教育的効果や財政的効果を生んでいます。
松原市のプールはこれまで大きな修繕工事もしてこず、水漏れ等にその時々で対応しているのが現状です。
約40数年経つ学校プールも建て替えると約2億円かかります。
昨今の異常気象ともいえる猛暑酷暑にプールの授業も中々時数が確保できない中で新しく建て替えてまで維持することが得策かどうか。
むしろ老朽化した市民プールを温水プール化し、一年中通してしっかりとしたプールの授業を確保することが可能となります。
その方が子ども達の泳力がつくのは間違いなく、インストラクターから学んだ方が泳ぐ楽しみはつくと信じています。
ましてやこれまで市民プールを利用していない高齢者までが健康増進に使えるようにすれば、医療費抑制にもつながり健康寿命の延伸も期待できます。
学校教育系施設の統廃合の中でプールの廃止という発想を取り入れることで新たな財源が生まれ、その中で児童生徒の移動に伴う経費やインストラクター等民間委託のコストも賄えると言った効果が得られるとこれまでの他の自治体の取り組み成果が発表されています。
そして、防災対策の観点から公立小中学校の防災機能強化の中長期目標では体育館の空調設置の目標が掲げられており、令和17年度には95%を目指すとしています。学校の授業は工夫をしながら暑い体育館での授業は避けられますが、避難所の指定を受けている小中学校において備えておかなくてなならない時代に来ています。
普通教室に設置された空調設備はライフラインが止まれば稼働しませんが、LPガスを活用した空調であれば3日間ほどは発電にも利用できます。万が一のリスク分散を考えておくことも防災行政を担う市の責務ではないかと考えます。
学校施設全体でのスクラップアンドビルドの発想で、是非とも前向きに考えて貰いたいところです。
将来を見据えた行財政改革を・・・
・公立中学校における運動部活動の地域移行の提言に基づく市としての今後の方針について
今年6月6日にスポーツ庁が所管する「運動部活動の地域移行に関する検討会議」から提言が出されました。
これまで学校単位とした中学校部活動が地域を拠点とした活動に令和5年度から3か年の改革集中期間に先ずは休日から移行しようとするものです。
内容はかなり分かりにくいものとなっていますが、要は少子化、教師の多忙化によって部活動が維持出来なくなってきている状況を鑑み、平日も含めて地域に頼っていこうという流れが始まりました。
かつて自分が中学生時代に過密な状態でサッカーの練習に明け暮れていた時代から思うと想像に難い状態が起こっています。
部活動を取り巻く諸問題を解消するための方策とはいえ、地域力が弱っている時代に応えるだけの土壌があるのかどうか。
もし指導者がボランティアであれば責任の所在が不明確ですので資格を持って指導的立場に立てる人が求められます。
教育の一環としてきた部活動も大きく転換することになりますが、良いものは残しつつ、中学生というとても人格形成の大切な時に空白のページを作らないように円滑な移行が進むことを願います。また、これにはスポーツマネジメント部がある地元の阪南大学とも連携し、より良い松原市の移行スタイルを構築して貰いたいと思います。
2022年11月28日 | 活動報告
令和4年11月28日(月)午前10時開会
令和4年松原市議会第4回定例会付議事件
・議案第61号 令和4年度松原市一般会計補正予算(第8号)
・議案第62号 令和4年度松原市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
・議案第63号 令和4年度松原市下水道事業会計補正予算(第1号)
・議案第64号 松原市都市公園条例の一部を改正する条例制定について
・議案第65号 令和4年度若林2丁目調整池築造工事請負契約について
・議案第66号 スケボーパークまつばらに係る指定管理者の指定について
議案説明がされましたが、本会議での議案質疑は無し。
各常任委員会で細かく質疑がなされる予定です。
今回の議案の中で主だったものは、
①一般会計補正予算(第8号)の中の電気・燃料・ガス料金高騰事業者支援事業
②同じく松原市新入学制・新社会人応援事業
③スポーツパークまつばらに係る指定管理者の指定について
だと思われます。
①については、昨今の国際情勢等による原油価格等の上昇により、影響を受けている市内事業者を支援するため、電気料金、燃料代及びガス料金の支払いに応じ、支援金を給付するものです。
②については、新たに市内の民間賃貸住宅に入居する新入学生・新社会人に対し、家賃相当額の一部を助成することで、若い世代の転入及び定住の促進を図るものです。
③については、新たに立部地区に建設される「スケボーパークまつばら」の指定管理者がミズノグループに決まり、それについて議決が必要となることから提案されています。
2022年11月15日 | 活動報告
令和4年11月15日(火)午後2時 諫早市「こどもの城」にて

この施設は市のHPでは情報が少なく、豊かな自然環境の中でのびのびと子どもが遊べるところという情報のみで訪問しました。
ただ、他の自治体議会も良く視察に来られることもあり、何か要因があるのではと期待も半分ありました。
場所は諫早市の山手を上がっていった白木峰高原に建設され、平成21年3月20日オープン、総事業費16億9500万円を投じて建設されました。
愛称「どわーの」で親しまれ、「どきどき・わくわく・のびのび」の頭文字をとった名前ですが、公募で決まったそうです。
屋外施設には、自然体験活動エリア、アスレチック遊具、水遊び場、砂場、ブランコ、木製デッキ、滑り台が完備されています。
また、屋内には全天候型の遊びスペースやごっごスペースがあり、団体利用にも対応できます。また多様な学習、体験活動が可能な「多目的利用」や「ものづくりスペース」などもあり、子どもだけでなく大人の利用も多いと聞きました。


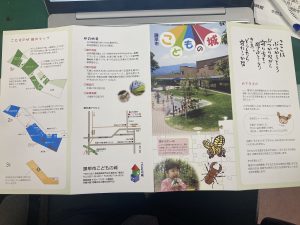
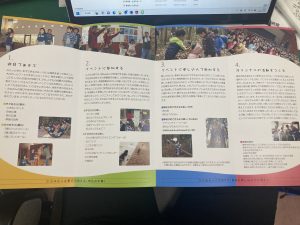
そもそも「こどもの城」ってどんなところかとの説明がありました。
年間で延べ約10万人の利用者、約200組の団体利用があり、運営は諫早市政策振興部と言うことでした。
最近は民間委託するところが多いですが、市直営であるからこそできる事があるとの思いで、前市長と現市長の考え方が受け継がれています。
来館者それぞれ目的が違います。

説明頂いた目標とは・・・
「恵まれた自然環境の中で子ども達の主体的な活動を促進し、子ども相互の交流を通して家族、その他子ども達を見守る人々の中で子ども達の生きる力を培う」
これは条例の理念と合わせており、何人来たからどうか・・・との部分で判断できるような施設ではないとのことです。
時間が無く、もっとお聴きしたいことがありましたが、駆け足での視察となりました。
しかしながらもっとも強く感じたことは「人」がこの施設、またこの施設に来られる方々を支えているということでした。
相談に来られた方が、今度はボランティアとしてこの施設で働かれる。
ひとことで言うと「心の拠り所」。




タテモノの中身がどうと言うことではなく、何を目的として施設を利用して貰うかが大事なんだと気づかされました。


松原市にも是非欲しい施設ですね・・・
2022年11月14日 | 活動報告

令和4年11月14日(月)午後2時30分
あぐりの丘に建設された「あぐりドーム」を訪れました。
この施設一体は以前はあぐりの丘として市が民間委託をして運営していた施設であったが、民間会社が撤退して、しばらくは市の職員で経営していたが、子育て世代のニーズ調査において、子どもの遊び場が欲しい、特に、雨の日や暑い日、寒い日など、天候に左右されない屋内の子どもの遊び場を求める声が多い状況であったことから、全天候型子ども遊戯施設を整備することになったとのこと。また、建設場所については広大な敷地と広い駐車場があり、まちなかでは体験しにくい自然や動物とのふれあいなどができ、屋外遊具エリアを中心に、子ども連れの来園者が多い、「あぐりの丘」に整備することになったと説明をお聴きました。

















施設内には乳幼児からまったりと遊ぶ親子がおられたり、小学生が飛んだり跳ねたり、ロッククライミングの体験もできる遊具もあり、様々な年代に合わせた物が並んでいました。
時間入れ替え制で過密になることなく安心して遊べる環境が羨ましいですね。
松原市には市内在住であり小学校低学年ぐらいまでしか遊べない屋内型の「チャレンジドーム」がありますが、年数も経ち、今の時代に合ったコンセプトから離れて行っている気がします。
他市からも注目を浴びる為には子育て世代に対する思い切った施設が無いと響かないのかなと感じました。
民間活力を使って今の子育て世代のニーズに合ったものが松原市にあれば・・・イメージも変わるのですが。
そんな思いも抱きつつ、施設内をゆっくりと丁寧に案内して頂いた長崎市こども部政策監の立木様に感謝申し上げます。
10月28日のオープン間もないお忙しい時期に突然の視察要請に応えて頂きありがとうございました。
2022年11月14日 | 活動報告
令和4年11月14日(月)午後1時 長崎市議会棟にて
人口約40万人。松原市の4倍弱、面積は約20数倍の406平方㎞のまち長崎市。
古くからの外国の文化の影響が色濃く残り、様々なところで融合された建築物が見受けられます。
中でも多くの修学旅行生がこの地を訪れており、この日もそうでしたが、1945年8月9日。運命の日。
原子爆弾が投下され、多くの犠牲者を生んだこの長崎で今は過去の様子をうかがい知ることも難しくなりました。
(この後、長崎原爆資料館もうかがって当時の多くの悲惨な資料を観て回りました。)
昨年10月には長崎市恐竜博物館がオープンし、11月には出島メッセ長崎の開業、今年9月には西九州新幹線が長崎に乗り入れられました。
交流人口が拡大をし、今後の雇用の創出や所得の向上が図れ、地域経済の活性化が期待できる地域であります。
また、来年1月には新市庁舎が開庁予定ともあり、様々な面で長崎市のこれからが楽しみであります。



そういった中、田上長崎市長がイクボス宣言をされたとの情報を得て、今注目されている父親の育児参加が進んでいるのか、また、仕事と休日の過ごし方のバランスが進んでいるのかといったワークライフバランスの観点で視察させていただきました。
事前質問に捕捉を加えながら説明して頂くやり方で45分進めて頂きました。
人事担当部署が旗を振るだけではやはり難しく、職員全体で自主的な取組を加速させなければならないという感触をつかんでおられ、まだまだ発展途上と言った感じを受けました。でも松原市よりもかなり前を進んでおられるのは間違いありません。
長崎市が行われた、「職場環境等に対する意識調査」では仕事量やワークライフバランスなど職員の働き方に関する項目でやりがいが低い結果が現れたとのこと。
こうした結果から、職員の働き方改革の実現に向けた取組みを進めることは喫緊の課題と認識され、新たに「ホワイト・ワークチャレンジ」としてスローガンを掲げ、重点的に取り組みを推進することとされています。
そのホワイト・ワークチャレンジとは・・・
経営層・管理職の「働き方改革に関するマネジメント力向上対策」と全職員による「仕事をやめる・へらす・かえる」プロジェクトを行い、組織全体で取り組む流れを作ろうとするもの。職員一丸となった取り組みにより計画上の目標の達成、ひいては職員全員がより良い展望を持って働けるようになるものと考えているとの説明を受けました。
また、イクボス宣言に対する質問では、市長の宣言は行っているものの、他の職員による宣言まで拡大できている状況になく、宣言による大きな反響があるという状況にないという段階だそうです。
そして、男性の育休が進むと職場内での仕事の配分が課題と思うところ、解消方法はどうされているかの質問では、職場での業務再配分も計画的に実施することが出来るよう所属長と育児休業を取得する職員があらかじめ休業の計画等について話し合いをしやすくするためのツールとして「育児介護参加プログラム」を作成するなどして、一定の取り組みは行ったものの、仕事の適正な配分の為には限られた人員の中で人員配置の在り方なども検討しながら進めていく必要があると考えておられるようで、現時点では大きな課題の一つであるとの認識をされていました。
まだまだこの分野では飛びぬけて進んでいる自治体は少ない、もしくは無いのかもしれません。
働き方改革と言われて多くの自治体が独自の方法で取り組まれています。
結局のところは、多様化する住民ニーズと人口獲得の意識が強くなることから生じる様々な取組に対する事務の負担がベースにあり、溶融なく働くことによる閉塞感、また職員間のコミュニケーション不足。負のスパイラルが行政サービス全体を覆っているように感じてなりません。
先進市視察を行ったつもりでしたが、どことも同じ課題を抱えていることを改めて実感した視察でした。
2022年11月14日 | 活動報告
令和4年11月14日(月)午前10時40分
大村空港に降り立った我々4人がレンタカーに乗り込みまず最初に向かったのは、諫早市が運営する「スポーツパークいさはや」
ここを訪れるきっかけは、金メダリストの西矢椛さんが昨年の東京オリンピックで輩出され、松原市において新たなスケボーパークの建設に向かい、今現在のスケートボードを取り巻く環境がどういうものか、またこれから整備するにあたり注意すべき点等を学ぶためでした。
全体的には施設の中心は2面の野球場及びサッカーコート。
2018年に供給開始となった約750平方メートルの規模を誇る公共スケートボード場です。




訪れた時には30代40代ぐらいの方々が滑っておられ、後ほど話を聴くことが出来ました。
管理者の人に施設の説明をお聴きし、平日は終日大人は110円、小人は50円と格安の料金。
さすがは公共のスケートボード場。
事前に質問を諫早市に送っていた回答も頂いた中で、やはり気になっていたのは騒音の問題。
市街地や住宅地での問題が起こっていたことから、この施設の整備計画に載せたとのこと。
ここであれば誰にも文句は言われず、伸び伸びと練習が出来ます。
スケートボード場で約3千万円。これはセクション作製費用とのこと。
整備に関しては一体工事の中に含まれているとのことでした。
またスクールに関しては、諫早スケートボード協会に委託し、令和4年7月から月1回のペースで実施されています。生徒は10名程度。
子どもが多くを占めています。
利用者はコンスタントにおられ、スケートボードの定着が感じられました。
単なる流行ではないことが来場者数からも見て取れ、松原市でも多くの利用者が期待できるのではないかと思います。
施設利用者の人が話しかけてきてくださり、これからのスケートボードの基盤、すそ野を広げていくには初心者が練習できる場所が必要であるとのこと。なるほど・・・。
ついついアクロバティックな演技を期待したり、偏った考え方の上級者がセクションを決めたりするとそういった罠に陥りがちだと仰っていました。
そして、飛んで跳ねてのスポーツなので路面の痛みが激しい。
なのでしっかりコンクリートに圧をかけて何層にもしておくとメンテナンスが楽だとも。
とても良くご存じだと思っていたら、大村市でショップをしているお兄さんでした(^^)
あとは野球場とサッカー場を軽く見学させてもらいました。






ありがとうございました。